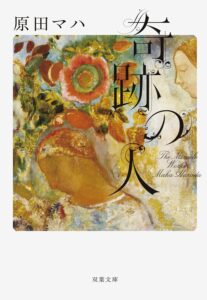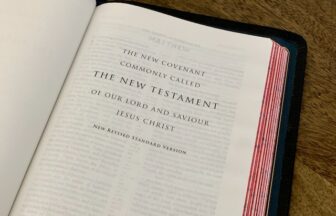私は次のように「キリスト教文学」を定義しています、「作者がキリスト教徒でない作家・詩人であったとしても、その文学的発想や営為の根拠に、キリスト教や聖書があり、そこからのメッセージと融和し、あるいは格闘しながらも、それに捕らえられ促されて表出する魂の文学である」と。
以下に取り上げる三人の作家は、私が調べた限りでは、キリスト者ではありません。しかし、これらの作品を生み出す力を補給し続けたのは、キリスト教であり、聖書なのです。
飯嶋和一『出星前夜』
飯嶋は、一九五二年、山形県山形市に生まれ、法政大学文学部を卒業後、中学校教諭、予備校講師などを経て、作家生活に入ります。
江戸初期に起きた「島原の乱」を、弾圧される側から重層的に描出した『出星前夜』(二〇〇八年)で第三五回大佛次郎賞を受賞しました。
キリシタン一揆として知られる島原の乱がなぜ起きたのか、二万七千人もの蜂起勢がほぼ全員殺害されるに至った経緯が緻密で重厚な筆致のもとに描かれますが、本作品においては、天草四郎(本書ではジェロニモ四郎)はあくまでも脇役です。
作者は、土に生きようとするかつての有馬家重臣の鬼塚監物(庄屋の甚右衛門)とイスパニア人を祖父に持つ青年寿安を描いて、「島原の乱」の真相を明らかにしていきます。乱の十年後、元号が慶安に変わって間もなく、一人の医家が大坂において開業しました。
ここの医者は、長崎に生まれ、オランダ人の血が混じっていると言われていて、逃禅堂北山友松と名乗っていました。その特異な風貌から「ジュアン」と通称されることが多くなります。スペイン名の Juanは「フアン、ホアン」と発音し、聖書によく登場してくるヨハネのことです。
貧窮する者には無償で施薬を行うため、昼夜休みなく診療を行っても寿安の暮らし向きは一向によくなりませんでした。いつの間にか「寿安サマ」という呼び名は、貧乏医者を指す代名詞として使われるようになります。
病児を抱える親たちが、とある星を「寿安星」と呼び、その星に快癒を願う姿が見られるようになったのは、北山寿安がこの世を去ってまもなくのことでした。
「出星前夜」とは、クリスマス・イヴのことではないのか、作者は作品を完成し発表してから、そのことに気づいたのではないか、と思われてなりません、読者がその深意に気づくほんの少し前に素早く。
『奇跡の人─ TheMiracle Worker』
原田は、一九六二年、東京都小平市に生まれました。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術専修を卒業し、馬里邑美術館、伊藤忠商事、森ビル美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館に勤務して、フリーのキュレーター(学芸専門委員)として独立します。
『楽園のカンヴァス』(二〇一二年)で第二五回山本周五郎賞と第五回R−40本屋さん大賞を受賞しました。続いて『総理の夫』『奇跡の人』『暗幕のゲルニカ』など矢継ぎ早に作品を発表しています。
ペンネームのマハは、インタビュー記事によれば、スペインの画家ゴヤの作品《裸のマハ》《着衣のマハ》に由来するそうです。二十代から美術評論家の高階秀爾に私淑しています。
小説『奇跡の人 The Miracle Worker』(二〇一四年)は、三重苦を克服して生きたアメリカの著述家・講演者であるヘレン・ケラーが書いた『奇跡の人─ヘレン・ケラー自伝』が元になっています。自伝では「奇跡の人」とは、ヘレンを導いたサリバン女史のことですが、小説では、弱視の去場安(サリバンがモデル)であるとともに、介良れん(ヘレン・ケラーがモデル)の二人を指します。
安は、「神の作りたもうたこの世界で、神のみもとで、私たちは、誰もが等しく学ぶ権利を持っているはずだ」というキリスト教信仰に励まされて、甘やかされ粗暴に育てられたれんと渾身の力で闘いながら彼女を導いていきます。れんとほぼ同世代の盲目の女旅芸人狼野キワが重要な役回りを引き受けていて、二人の魂の温かな交感がきめ細やかに語られます。
物語は、安とれんのすさまじい闘いが繰り広げられた一八八七年の過去を、一九五四年と五五年のキワを描いた穏やかな現在が前後に挟み込むような構成になっています。
過去の主たる舞台は、青森県北津軽郡金木町です。そこは紛れもなく作家・太宰治の生まれ故郷ですから、作者の太宰に対するオマージュ(敬意)が間接的に暗示されていると言えます。
自伝同様、小説においても、指文字によって言葉と物との関係をれんが初めて認識して回心する場面は感動的です。聴力を失う以前に聞いて声に出して言ったことのある「水」という言葉が、実体の水と一つにつながった極めて大切な瞬間でした。
角田光代『方舟を燃やす』
角田は、一九六七年、神奈川県に生まれました。早稲田大学第一文学部文芸専修を卒業して作家生活に入り、『対岸の彼女』で二〇〇五年に直木賞、『八日目の蟬』で二〇〇七年に中央公論文芸賞、本書で二〇二五年の吉川英治文学賞を受賞しています。
エッセイによれば、幼いころからプロテスタントの教会が運営していた保育園や同系の小学校に通い、礼拝し聖書を読み賛美歌を歌っていたとのこと。高校卒業後は、キリスト教から少しく距離を置いていると述べています。
この小説名にある「方舟」は、紛れもなく旧約聖書創世記に登場するノアの方舟のこと。主要な登場人物は柳原飛馬と望月不三子です。
飛馬が生まれたのは一九六七年で、育ったのは、神戸の山間の小さな町。世界が滅びるというノストラダムスの大予言を信じたこと、最愛の母を子宮がんで喪ったこと、占いの一種コックリさんに夢中になったこと、東京の大学に進学し、公務員の道を歩むことになったことなどが淡々と語られます。結婚しますが円満に離婚、一人の生活を始め、ボランティアに専念します。
不三子が生まれたのは、敗戦直後。キリスト教系の病院へバスで通ったこと、礼拝にも参加したこと、玄米中心の食生活をしてきたこと、三種混合ワクチン接種に悩んだこと、自然療法や食事法に凝ったこと、加えて関西を襲った大地震も経験します。夫に先立たれますが、現在、娘、息子とも必ずしもいい関係を築けてはいません。
年齢も育った環境も異なる二人が、何年かを経て静かに出会ったのは、教会が運営していた子ども食堂でした。二人ともボランティアとして働きますが、教会という隔ての中垣を楽々と越えています。やがて新型コロナが流行し、人々は極度の制限を受け始めます。そんな中でも教会の子ども食堂は再開されます。何を生きる糧として選ぶのか、様々な情報に翻弄される主人公たちが描かれます。
小説の最終部で、大型台風が襲来し、避難指示が出ます。飛馬はひとり暮らしの不三子を避難させるために彼女の家を訪ねますが、その不三子が子ども食堂で気にかけてきた母子家庭の少女園花も連れていくと言い出します。その少女が今度はいるかいないか分からない公園の野良猫を気にかけます。
不三子は、教会で聞いたことのあるノアの方舟のことを想起します。「神さまを信じた男の家族と動物たちだけは、助かって生き残る。(中略)神さまの世界はなんと秩序だっていて、人間の世界はなんとはちゃめちゃなんだろう。」その直前に不三子は、巨大な建物が燃えるさまを脳裡に思い浮かべていました。
書名にふさわしいと思われる「燃える」という自動詞が、なぜ「燃やす」という悪意を含みそうな他動詞にあえて変えられているのか。疑問は疑問のままにその解釈は読み手にすべて委ねられることになります。
私は、実人生にやってきた噂や予言や有象無象のこだわりを方舟に閉じ込めるだけではなくて、焼き滅ぼすほどの強い意志を込めた結果なのではないかと思っています。