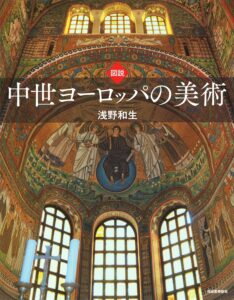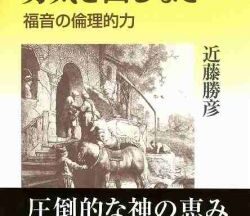二〇二二年から二三年にかけて、スコットランド国立美術館、ドレスデン国立古典絵画館、ルーブル美術館など、ヨーロッパの主要美術館が所蔵する作品を日本で公開する展覧会がいくつも開催されてきました。こうした展覧会には、必ずといっていいほどキリスト教をテーマとする作品が含まれています。作品情報(主題、作者、制作年、注文者、制作当時の時代背景など)について知りたければ、作品のキャプション、イヤホンガイド、展覧会カタログの解説などが参考になります。
それでは、展覧会に出品されている作品にとどまらず、キリスト教美術全般についてもっと知りたいと思った時には、どのような本を手に取ればよいでしょうか。聖書の中のどの場面を表す作品なのか知りたいなら、山形孝夫『図説聖書物語旧約篇』や『同新約篇』の図版付きの解説があります(いずれも河出書房新社)。さらに、歴史の流れに沿ってどのようにキリスト教美術が展開していったのかを知りたい場合には、西洋美術史の概説書が役に立ちます。たとえば、水野千依編『古代から初期ルネサンスまで』や『盛期ルネサンスから十九世紀末まで』(京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎)などです。こうした書物をひもとくことで、展覧会場で見かけたある作品が、キリスト教美術の大きな流れの中でどのように位置づけられるものなのか、さらに理解を深めることができるでしょう。
残念なことに日本で紹介されるキリスト教美術というと、どうもルネサンス以降の西ヨーロッパの美術に重きが置かれる傾向があります。キリスト教美術には、ルネサンスのはるか以前にまでさかのぼる長い歴史があるのですが、その源まで立ち戻って全体の流れをたどる書物を書くというのは、なかなか容易なことではないからです。また、ロンドンやニューヨークで、中世キリスト教美術、ビザンティン美術を取り上げる大きな展覧会が開催されることはあっても、日本でそのような展覧会が開かれることはほぼありません。そこでこのコラムでは、キリスト教美術史を学びたい皆さまに、日本ではほとんど触れる機会のない、ルネサンス以前のキリスト教美術について語る三冊をご紹介したいと思います。
『初期キリスト教美術・ビザンティン美術』(ジョン・ラウデン著、益田朋幸訳、岩波書店)
一点目は『初期キリスト教美術・ビザンティン美術』(ジョン・ラウデン著、益田朋幸訳、岩波書店)です。著者のラウデンは、ロンドン大学コートールド美術研究所で教壇に立っていた人で、ビザンティン写本挿絵研究の第一人者です。本書では、写本挿絵のみならず建築、壁画、イコン、象牙浮彫、七宝、金銀細工など数多くの作例が取り上げられ、千年に及ぶビザンティン美術の歴史が語られています。ページをめくりながらカラーの図版を眺めてみるだけで、いわゆる名画でたどるキリスト教美術の本とは大きく異なる印象を持つことになるはずです。
本書の構成は、「イコノクラスム以前の美術」「イコノクラスム」「ビザンティン美術の拡散」という大きく三つに分けられているのですが、その理由は、イコノクラスム(聖像破壊運動)という出来事が、ビザンティン帝国におけるキリスト教美術の流れを、いったんスッパリと断ち切ってしまったからです。ラウデンは、この聖像破壊論争が、後のビザンティン美術の方向性をいかに決定づけたかという点に注目することで、ビザンティン美術の本質を捉えようとしています。
ラウデンはまた、ビザンティン美術の本質が、ルネサンス以降の「芸術の進歩」という概念とは相いれないものであることを強調します。わたしたち現代人の常識から考えて、歴史の流れの中で世界が変化しないということは、ほとんどありえないことですが、ビザンティン帝国の世界観とは、神の代理人である皇帝を頂点とした地上世界は天上の神の国の写しであり、したがって地上の帝国の秩序は変化なく永遠に存続していく、というものでした。したがってビザンティン美術は、そのような理念のもとに作られたものであり、この点において西洋中世の美術やルネサンス以降の美術とは大きく異なっています。
『図説 中世ヨーロッパの美術』(浅野和生著、河出書房新社)
二点目は、『図説 中世ヨーロッパの美術』(浅野和生著、河出書房新社)です。浅野は、トルコでキリスト教建築の発掘調査に長年携わっていた人です。本書は、そもそも中世とはどこからどこまでを含む時代で、中世美術とはどのような特質を持つものだったのか、というところから始まります。本書の一番の特徴は、西洋美術史の概説書にありがちな、年代ごと(様式ごと)の章立てではないという点です。カロリング朝の美術、オットー朝の美術、ロマネスク美術、ゴシック美術という順序ではなく、都市ローマの聖堂と装飾、カテドラル建築(ケルンやピサなど)、てのひらサイズの小さな七宝や象牙、そして中世特有の聖人信仰という章立てで展開していきます。中世の建築が多く残されている都市を訪れる章や、中世以来現代にまで引き継がれてきた修道院を訪れる章を読んでいると、著者とともに中世の町中をあちこち歩き回っているかのような感覚にとらわれます。
また、美術作品や絵画技法の解説にとどまらず、当時の人々のありようと美術との接点を浮かび上がらせる記述が散りばめられています。たとえば、芸術の寄進者となった支配層、数十年(あるいは数百年)におよぶ大聖堂の建築作業を寄進によって支えた人々、病の癒やしを願って聖人により頼んだ人々、戦争や略奪に苦しめられた人々、国王と対立するほどの権力を手にした司教、僧房に暮らす修道士たち、工房で制作に携わる職人や画家、聖地へと旅する巡礼者、地中海をまたぐ異文化の交流。そのような社会において、中世の人々がキリスト教の信仰のために芸術をどのように作り上げ、また受容していたのかという点が、多くのカラー図版とともにわかりやすくまとめられています。
『キリスト教美術史 東方正教会とカトリックの二大潮流』(中央公論新社)
三点目として、筆者の近著『キリスト教美術史 東方正教会とカトリックの二大潮流』(中央公論新社)をご紹介したいと思います。本書は、上に紹介した初期キリスト教美術とビザンティン美術、そして西ヨーロッパ中世のキリスト教美術、その両方を含む構成で、かつ両者の違いを対比する視点を持って書かれたという点が特徴的です。
ローマ帝国時代、キリスト教美術は信仰の表明や葬礼を目的として成立しました。やがて四世紀末に帝国は東西分裂し、ここからキリスト教美術の二つの潮流が生まれることになります。一方は、千年以上の長きにわたり不変であることを誇った正教会の美術。他方は、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックと様式が変転していったローマ・カトリック教会の美術です。
本書は、従来の西洋美術史の概説書と同じく、古い時代から順に時系列で話を進める通史の体裁をとった章立てではありますが、単なる美術様式の歴史にとどまらない記述を目指しました。概説書によくあるような、様式の歴史を時系列に沿って語るやり方、あるいは西洋史の流れの中に美術作品をあてはめて語るやり方ではないということです。それよりも、一つひとつの作品それ自体と正面から向き合うことを重視しました。何が描かれているのか、なぜそのように描かれたのか、作品はどのようなメッセージを伝えているのか。そのような問いを立てることで初めて見えてくる、キリスト教美術が持つ根源的な力に触れるような書物にしたいと願ったからです。
初期キリスト教美術とそれに続くビザンティン美術(ラウデン)、そこから枝分かれしていった時代の西洋中世美術(浅野)、その両方を対比しつつ、キリスト教美術の流れを源までさかのぼって見渡そうとする本書。この三冊を読むことで、ルネサンス以降の名画を並べた西洋美術史の本からは見えてこない、キリスト教美術のエッセンスに触れることができるでしょう。そして、今後展覧会に出かけてキリスト教絵画を見かけた時、これまでとは違った見方ができることに気づくはずです。