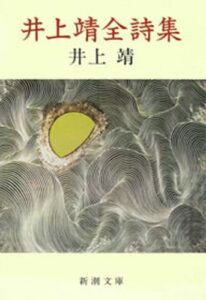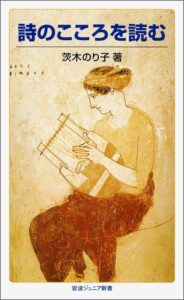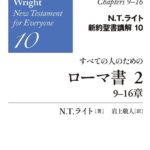「詩を書くならこの三冊」という課題を与えられて、私には戸惑いと逡巡があります。この三冊を読めば詩が書けるようになるかと言えば、そんなことはありません。私の歩みを振り返ると、詩を書いていく継続力は、どれだけ先人の詩に魂を揺さぶられる経験をしてきたかにかかっているように思われてならないからです。
私が初めて教会で礼拝し、下宿の四畳半の部屋に戻ってから、急に詩が書きたくなって書き始めたのは、もう六十年も前のことになります。
折に触れて詩の案内書を読んできたことはありますが、それらの本に直接促されて詩を書いたことはないと思います。今でも影響を受けているのは、村野四郎著『現代詩を求めて』(社会思想社)、山本太郎著『詩の作法』(社会思想社)でした。
村野の案内書から私が得たものは、「詩は「言葉」以外に表現する素材を持たない」という潔い覚悟であり、「詩は、古くなった言葉にたえず新しい生命をよみがえらせるもの」であるという至極簡潔な励ましの言葉でした。
言葉以外に表現する手段を持たないという不自由さが、思いも寄らないぎりぎりの表現を生み出すのであり、疲れきった言葉の再生復活を果たすのだということでした。
それに加えて、山本から与えられた次の促しでした。「「そして・だが・しかし・けれど・すると・と突然・したがって・とはいえ……」などの接続詞、もしくは接続詞的要素を出来るだけ使わないようにしましょう。」この勧めは、若かった私には衝撃的なものでした。それからは、単に文と文を結ぶ機械的な働きしかしていないような接続詞の使用に極力抑制的になりました。
これから紹介する詩集二冊と評論一冊は、どれも私にとって大切な詩集と案内書になりました。
井上靖著『井上靖全詩集』
井上靖(一九〇七─九一年)は、『猟銃』『闘牛』『氷壁』『風林火山』『天平の甍』『おろしや国酔夢譚』『敦煌』『孔子』などで知られる小説家ですが、私にとっては、それ以上に詩人です。
彼は、行分け詩をほとんど書きませんでした。行分け詩を捨てて「散文詩一辺倒になったのは、行分け詩が、歌うことに流れるのを意識して抑制したからだ」と言います。
全詩集に収録されている詩集は、『北国』『地中海』『運河』『季節』『遠征路』ですが、その中から詩集『北国』に収録され、その後小説名にもなった「猟銃」という詩を引用します。
猟 銃
なぜかその中年男は村人の顰蹙を買い、彼に集る不評判は子供の私の耳にさえも入っていた。
ある冬の朝、私は、その人がかたく銃弾の腰帯をしめ、コールテンの上衣の上に猟銃を重くくいこませ、長靴で霜柱を踏みしだきながら、天城への間道の叢をゆっくりと分け登ってゆくのを見たことがあった。
それから二十余年、その人はとうに故人になったが、その時のその人の背後姿は今でも私の瞼から消えない。生きものの命断つ白い鋼鉄の器具で、あのように冷たく武装しなければならなかったものは何であったのか。私はいまでも都会の雑踏の中にある時、ふと、あの猟人のように歩きたいと思うことがある。ゆっくりと、静かに、冷たく──。そして、人生の白い河床をのぞき見た中年の孤独なる精神と肉体の双方に、同時にしみ入るような重量感を捺印するものは、やはりあの磨き光れる一個の猟銃をおいてはないかと思うのだ。
小説を思わせる緊迫した書き出しです。その佇まいの厳しさの理由は、詩の中心に非情とも言える猟銃を据えているからです。詩の語り手は、「二十余年」も前の出来事を振り返っています。この詩がずしりとした重みを持っているのは、鋼鉄の器具を仔細に描写しているからです。
どれだけ人と物との関わりを見据えて描写できるのか、そこにこそ詩の並々ならぬ潜在力があります。
石垣りん著『石垣りん詩集』
石垣りん(一九二〇─二〇〇四年)は、長年銀行員として誠実に勤務してきました。詩集『私の前にある鍋とお釜と燃える火と』『表札など』『略歴』『やさしい言葉』などで知られる詩人です。日常茶飯の平明な言葉を用いて詩を書きましたが、一見した印象とは異なり、詩の中に読み手の意表をつく批評精神を隠し持っていることがあります。詩集『表札など』の標題詩「表札」を紹介します。
表札
自分の住むところには
自分の表札を出すにかぎる。自分の寝泊りする場所に
他人がかけてくれる表札は
いつもろくなことはない。病院へ入院したら
病室の名札には石垣りん様と
様が付いた。旅館に泊っても
部屋の外に名前は出ないが
やがて焼場の鑵にはいると
とじた扉の上に
石垣りん殿と札が下がるだろう
そのとき私がこばめるか?様も
殿も
付いてはいけない、自分の住む所には
自分の手で表札をかけるに限る。精神の在り場所も
ハタから表札をかけられてはならない
石垣りん
それでよい。
木製なのか陶器製なのか分かりませんが、ここにはどの家にもあるはずの表札が取り上げられています。難しい言葉はいっさい使われていません。この詩人が伝えたいことはひしひしと伝わってきます。それが私たちの生き方を問うてくるのです。表札一つの在りようから、詩人の凜とした姿がすっくと立ち上がってきます。
茨木のり子著『詩のこころを読む』
茨木のり子(一九二六─二〇〇六年)は、詩人、エッセイスト、童話作家、脚本家でした。主な詩集に、『見えない配達夫』『鎮魂歌』『自分の感受性くらい』『倚りかからず』などがあります。この案内書は、私が人生最大の危機に直面した時期に病院の待合室で読み、深く慰められ励まされたた本でした。
「はじめに」において「いい詩には、ひとの心を解き放ってくれる力があります。いい詩はまた、生きとし生けるものへの、いとおしみの感情をやさしく誘いだしてもくれます。どこの国でも詩は、その国のことばの花々です」と著者は語り出しますが、まさにこの案内書自体が花々に溢れています。
三十人の極上の詩群が選ばれ、その作品に対して愛情に満ちた解釈が施されています。それぞれの詩人の人柄ならぬ「詩柄」が私たちの魂深くに分け入り、愛情が発掘され解放されます。
まとめ
伝えたいことがすでにはっきりしていて書く詩よりも、書いていくことによって、作品の意図が次第に明確になり、本人も驚きながら味わえる詩に私は魅かれます。
詩を数多く読むこと、それらに感動する自分を愛おしむこと、日常の中で非日常を見つけることに喜びを覚えること、本稿の課題への私の答えです。