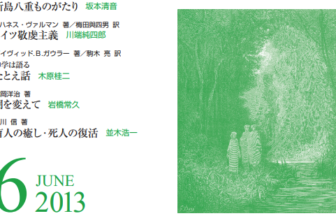三浦綾子と言えば、一九六四(昭和三九)年、「生まれてはじめての小説」である『氷点』が朝日新聞社一千万円懸賞小説に当選し、鮮烈なデビューを果たした作家である。また、クリスチャンとして「小説を書くことは信仰生活なのである」「キリストの福音を伝えようとして書いている」と明言し、作家活動を続けたことでも知られている。
テレビドラマ化され、第一回から22・6%の視聴率で最終回には42%となって世を騒がせ、ブームとなった『氷点』もテーマは〈原罪〉であった。三浦と同じ日本キリスト教団旭川六条教会の明治の頃の教会員で、塩狩峠の鉄道事故で亡くなった鉄道員・長野政雄を原型とした『塩狩峠』は〈犠牲〉、拷問によって悲惨な死を遂げたプロレタリア作家・小林多喜二をその母・セキが語る『母』は〈ピエタ〉、十勝岳噴火とそれに伴う火山泥流に襲われる開拓農家を描いた『泥流地帯』、また『天北原野』も「善人が、なぜ故なき苦難にあうのか」というヨブ記に示される〈苦難〉であった。
このような三浦綾子とその文学に対して、戸惑いと批判は当初からあった。近代文学の伝統においては三浦のようにキリスト教、つまり宗教を全面的に打ち出した作品は、護教文学、宣教文学、もしくは主人持ちの文学としてその文学性に疑義がもたれるのが常だったからである。しかしながら三浦は、このような戸惑いや批判を承知の上で数々の作品を書き続け、その作品は確実に読者を得てきた。さらに言えば、そのような読者の中から多くの受洗者を生み出してきたのであった。
信仰の土台にしかと立つ作品を世に送り出し、深い共感と支持を多くの読者から得てきた三浦綾子とその文学を「現代の奇蹟」と評したのは佐古純一郎であるが、このような三浦の作品は、文庫をはじめとする紙媒体だけでなく、今は全て電子書籍化され、「三浦綾子電子全集」(小学館)で読むことができる。また、『氷点』の舞台でもある旭川市の見本林(外国樹種見本林)に建つ三浦綾子記念文学館では、所蔵の資料調査から発見された三浦綾子およびその文学に関する出版がその時々になされている。
二〇二二年は三浦綾子の生誕百年であるが、これを契機に三浦綾子をもっと知るために取り上げてみたいのは、次の三冊である。
三浦綾子・三浦綾子記念文学館編著 『「氷点」を旅する』
『氷点』が世に出て四〇年の節目の年に出版された。序の「三浦綾子がつづるあらすじ」は、三浦が朝日新聞社に応募する時に提出した「あらすじ」で未発表(三浦綾子記念文学館所蔵)のもの。応募時の『氷点』のおおよそが分かり、『氷点』の深読みに誘われる。たとえば、戦中、戦後の設定だった応募時から戦後の出来事に変わった発表作品では、その日常性が強調され、今もなお読者を惹きつけるものとなっていることが自ずと理解できる。また、陽子の実母の登場など、のちの『続氷点』につながるものが応募時から既に存在していたことも興味深い。
このように『氷点』の魅力について改めて考えさせられる本著は、同時に第五章「その時代は氷点をどう読んだか」を中心に、一九六四年という戦後日本の大きな変わり目である時代が生み出した作品であることを詳らかにする。
作品のテーマ〈原罪〉は特異なもののように思われるが、遠藤周作が『沈黙』を書き下ろしで発表したのは一九六六年。また、時代小説の泰斗で独自の作品世界で今もなお多くの読者をもつ山本周五郎の中絶した最後の作品『おごそかな渇き』(一九六七)は「現代の聖書」を書くと述べて取り組んだものであった。
「戦後文学の変種」と『氷点』を喝破したのは文芸評論家で三浦綾子記念文学館初代館長であった高野斗志美だが、「もはや戦後ではない」(一九五六年経済白書)が当然のこととなったこの時期、戦後文学が向きあった根源的なものが宗教、とりわけキリスト教に関わって浮上してくる、そのような中に三浦とその作品もあったのである。
現在、本著は絶版になっているが、『氷点』と合わせて『氷点 特装版』となる予定と聞き、ここに紹介することにした。
三浦光世 『青春の傷痕』
三浦の作品は、『塩狩峠』の頃から、三浦の口述を夫・光世が書きとめるといういわゆる口述筆記によるものであった。十三年間の結核療養生活を経験した三浦のおもに健康上の理由からではあるが、この執筆スタイルがじつは三浦文学の本質に関わるものであり、三浦文学はコラボレーション(協働)をその特質とするとかつて指摘したことがある。この考えは今も変わらないが、コラボレーションとは、ジャズのジャム・セッションや連歌・連句などのようなもので、創造的な行動や関係の中でつねに生じ、「いわゆる通信情報の閉鎖系のコードではなく、自己言及をふくむメタフォリカル(隠喩的)で物語的なオープン・コード」(井上輝夫「ポスト・モダンとコラボレーション」)を特徴とする。
自宅二階の茶の間のような仕事部屋で向き合い、三浦が語る言葉を、一区切りごとに「ハイ」とか「うん」とか返事をしながら最初の読者として作品を受け止めていく光世を前に、三浦の創作はいっそうリアリティーをましていく。このような執筆の様子は、書斎に閉じこもって一人呻吟しつつ執筆するという従来の作家の姿から程遠い。〈同行二人〉ともいうように、〈共にあること〉は宗教の本質である。そのことを証しするかのような光景が三浦の仕事部屋では繰り広げられていた。
本著は、このような口述筆記で三浦綾子を支え、共に歩み、名実ともに最良のパートナーであった夫・光世の自伝である。
東京生まれの光世は、三歳の時に家族とともに北海道に移り住む。結核になった父が、自身が開拓して両親を呼び寄せた滝たきのうえ上に戻ることを決意したからであった。まもなく父は三二歳で死に、母は手職を身につけるために三人の子どもを残して家を出た。光世は母方の祖父の家に預けられ、育った。この祖父は、二〇歳頃に洗礼を受け、旧約聖書をよく読んでいた。以上のような光世の生い立ちは、やがて『泥流地帯』になぞるように描かれていくが、この『泥流地帯』のみならず、光世の経験や体験、また光世とのやり取りが作品成立に関わったり、また組み込まれていることを本著は明らかにしてくれる。
本著は、「三浦光世 電子選集」(小学館)でも読むことができる。
石井一弘 『愛のまなざし―三浦綾子の舞台を旅する―』
三浦綾子は文学アルバムや写真集が多い作家でもある。『文学アルバム』(主婦の友社、一九九一)をはじめとする『幼な児のごとく/三浦綾子文学アルバム』(北海道新聞社、一九九四)、『生きること ゆるすこと/新文学アルバム』(北海道新聞社、二〇〇七)、また『写真集 遥かなる三浦綾子』(近藤多美子・写真、講談社出版サービスセンター、二〇〇〇)、『永遠に・三浦綾子写真集』(後山一朗・写真、北海道新聞社、一九九九)などがすぐさま思い浮かぶ。
本著は、『氷点』と同じ一九六四年に朝日新聞社に入社し、カメラマン生活に入った著者が、定年後に三浦の作品の舞台を撮りはじめ、三浦の没後一〇年で三浦の文章と写真で構成した『小さなロバ』を、さらにその一〇年後に作品に関する写真に自身の文章を加えて出版したものである。
写真が充実しているのは当然のことながら、そこに文章が加わることで本著では、写真と文章が呼応し合った、相即不離と言って良いか分からないが、不思議な場が醸成されている。それは物語というべきものなのかもしれないが、そのような世界に入り込んだ私たちは、著者と一緒にひととき三浦綾子の舞台を旅する。『氷点』は陽子が自殺を図った美瑛川流域の雪原だけでなく、アイヌ墓地の写真なのですね、などと時に対話しながら、三浦綾子とその作品世界を満喫できる一冊となっている。