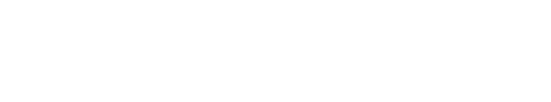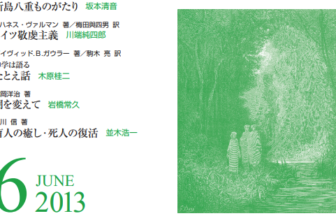今号の「この三冊!」は本ではなく映画を取り扱うことになりましたので、「この三本!」としてご紹介いたします。
キリスト教を取り扱った映画はいくつもあります。しかし、聖書の物語を脚色したり解釈し直すような映画は多い一方で、神の存在や信仰を根本から問い直すような物語を描くような作品は少ないように思います。
これからご紹介するのは、そのような「変わり種」の作品です。いずれもアクション満載で、視覚効果をふんだんに用いた娯楽性の高い作品ながら、宗教者に突きつける問いは鋭いものです。
なお、本稿の中で、ややネタバレ的になってしまうのは否めませんが、鑑賞の妨げにならない程度に極力抑えるつもりです。
『ジャンヌ・ダルク』(Joan of Arc)
一九九九年、リュック・ベッソン監督、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演。
純真で信仰心が篤く、霊的な直感が豊かなフランスの少女ジャンヌが、戦乱のなかで成長し、百年戦争下の流血の地獄に身を投じて暴れ回る物語です。
英国軍の荒くれ者たちに村を焼かれ、目の前で姉を犯され、殺された、その絶望と憤怒がジャンヌの原動力となっています。しかし、それに劣らず、さらに深いところから彼女を突き動かしているのが、幼い頃から彼女が体験し続けた神秘体験です。
「なぜ自分は生き残ったのか」と泣きじゃくる少女ジャンヌに対し、告解室の神父も神が何を望んでおられるのか答えることができません。にもかかわらず、そこで神父は「神はおまえが必要だからお前を選んだのだ」と告げてしまいます。ジャンヌは「今すぐ神とひとつになりたい」と望み、そこから彼女の神秘体験は更に深く強烈なものとなって、彼女は自分の召命感が絶対であるとの確信を抱いてゆきます。
しかし、物語の終盤、ジャンヌは自分が聞く神の声の正体が本当は何者なのか、大いなる疑問に直面することになります。彼女の心の中に、「試みる者」が現れるのです。この「試みる者」による問いはとても重要です。
なぜなら、それは神の存在への疑問のみならず、これまでの歴史上行われてきた幾多の戦争に対する、根本的な問いでもあるからです。人間は「神はなぜ平和を与えてくださらないのか」と言いながら、自らの手を血で汚します。なんと身勝手で自己都合の理屈でしょうか。
この映画は、「神は平和の神ではないのか」「なぜ戦争に神は介入しないのか」と問う者に、「戦争を起こしているのは人間であり、その人間が神を戦争の道具に貶めているだけではないのか」と、逆に問い返しているように思えます。
神とは他者なのか。「啓示」は「本物」なのか。それとも、私たちは自分の見たいものを見、聞きたいことを聞いているに過ぎないのか。
そんな問いを突きつけながら、物語は大いなる皮肉によって締め括られることになります。
『エクソダス 神と王』(Exodus: Godsand Kings)
二〇一四年、リドリー・スコット監督、クリスチャン・ベール、ジョエル・エドガートン主演。
“Gods and Kings”という副題は、神と神、王と王の戦いを表しています。片や自分こそがエジプトの神だと主張するファラオであるラメセス。片や奴隷たちの王モーセ。
モーセが初めて神と出会うのは、夢の中です。またその後、何度か彼は神と対話していますが、第三者から見ればそれは独り言に過ぎず、この映画では、神は彼の幻視であるかのように描かれています。
この神は名を尋ねられて「わたしだ(I am)」とだけ答えます。この「わたしだ」は、かなり好戦的な神です。モーセの前に現れて、いきなりエジプト人との戦いをけしかけ、反乱のリーダーとしての使命をモーセに与えようとします。しかも、モーセの戦いが物足りないと思うや否や、今度は自らが力を下し、エジプトの民を叩くのです。
ここに登場する神が、モーセ自身のもうひとりの「わたしだ」であるならば、これはモーセ自身に潜む攻撃性を表しているのかもしれません。これはヘブライ人(ユダヤ人)の二面性を象徴していると読み取ることもできます。一方では奴隷制や虐殺の被害者でありながら、他方では好戦的な抑圧者という面もあるからです。
実際モーセは、自分たちがカナンの地に入る時には侵略者となることを予知しています。自分たちの民が国を築けるほど多いから問題なのだと言っています。これには、イスラエル批判の意図も込められているのではないか、と私は思います。
あるいは、モーセと「わたしだ」との対話は、宗教心と人間性との葛藤を表していると解釈することもできます。宗教心は権利を勝ち取るために暴力を行使する危険性を持ちますが、人間性はそんな宗教心における攻撃性を抑制しようとするのです。
この映画では人間よりも神の方が暴力的です。そこに映画作家の宗教観がよく表れています。神は退場するべき存在であり、本当に人間を存続させるのは人間性なのだ、という主張を読み取ることができます。実際、物語の最後で神は退場し、モーセが石に刻んだ法が民を治めるようになるのです。
(この映画には壮絶な津波のシーンがあります。鑑賞には配慮が必要でしょう。)
『ノア 約束の舟』(Noah)
二〇一四年、ダーレン・アロノフスキー監督、ラッセル・クロウ主演。
上述の二本と異なり、リアリティを追求した歴史物の体裁ではなく、聖書にあるノアの物語を大幅に翻案し、新しいファンタジーとして描きなおしたものです。
この映画では、超越者は「神」ではなく、一貫して「Creator(クリエイター:創造者)」と呼ばれています。一神教的世界観における創造論に基づいた神観であることは間違いないのですが、それでもできるだけユダヤ教、キリスト教にとらわれない普遍的な物語として語ろうという意図があるのかもしれません。
このクリエイターは、何らかの姿をとって現れたり、はっきりとした声で言葉を聞かせたりはしません。「彼」はノアに、夢の中や薬を介した幻覚などを通して、物語としてのヴィジョンを見せ、自らの意図を読み取らせようとします。
ノアが自分の見たヴィジョンを家族に話す場面で、クリエイターが宇宙や地球、そして地上の楽園を築いてゆく様子が描かれます。これは非常に美しいものです。この映像には、地球や生物の創造についての物理学的、進化論的な解釈が行われていますが、ここは宗教界では賛否が分かれるところでしょう。
そして、このヴィジョンで示されるのは、いかに人間が互いに殺し合うことで歴史を形作ってきたかということでもあります。人間の「罪」は、暴力の連鎖なのです。
クリエイターから与えられた(とノアが解釈した)使命は、人類を罰し、完全に絶滅させるというものでした。人間さえ生まれなければ楽園は永遠に続いたのに、人間が全てをぶち壊してしまいました。ですから人間を地上から一掃し、人間なしの楽園を一から再生するのがクリエイターの意図だというのです。そして、その使命を遂行するために選ばれたのがノアなのでした。
ノアの終生のライバルが、カインの末裔であるトバル・カインです。トバル・カインは、人間こそクリエイターに似せて造られた者であり、全ての生物の上に君臨する最も偉大な生物だと主張します。しかし、その偉大な人間のしるしは、武器を作って人間どうし殺し合うことでもあります。トバル・カインにとっては、人を殺すことができるのが人間であることの証しなのです。
これは二つの極端な人間観の対決です。一方は、暴力こそが人間の証しだとするような罪深い存在は地球にはいないほうが良いのだという思想。もう一方は、あくまで人間こそが万物の霊長であり、戦い、殺し、奪ってでも、生き残り、成長し続けなくてはならないのだという思想です。
人間は滅ぶべきか。生き延びるべきか。人間が生き延びるためには、地球を破壊し、他の生命を殺し続けなくてはなりません。それを阻止するのがクリエイターの意図だとノアは信じています。
しかし、ある予想外の出来事から、ノアは自分の使命を遂行できなくなってしまいます。ノアが信じる「正義」とは異なる、もう一つの人間観への気づきです。そこにノアは、「正義」とも「罪」とも違う、何か善いものを発見し、自分たち自身が新しい人類となって再出発する道に導かれてゆきます。ひと言も言葉を発しないクリエイターの真の意図も、最後の場面で示されることになります。
以上、三本の映画をご紹介しました。
暴力の源泉と責任はどこにあるのか。神は人間の暴力にどのように関与するのか、あるいはしないのか。
賛否はともかく、これらの作品は、娯楽として楽しみつつ、思索の材料とすることもできる、そんな両面を兼ね備えた映画として大変優れたものです。まだの方は、ぜひ鑑賞することをお勧めいたします。いずれもインターネットによる登録制の映画配信サービス(アマゾン・プライム・ビデオなど)で視聴可能です。

富田正樹
とみた・まさき=同志社香里中学校・高等学校教員